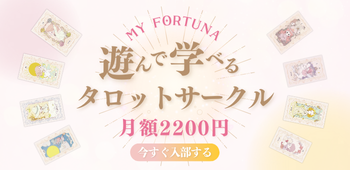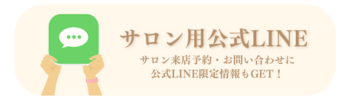茨城県水戸市双葉台|JR赤塚駅最寄り
水戸内原イオンから車で10分|水戸IC近く
水戸内原イオンから車で10分|水戸IC近く
疲労感は危険信号!
2025/02/27
皆さん、いつもお疲れ様です!
前回から引き続き、雑誌THE 21から抜粋した内容の続きをお送りします!
疲労感とは
日本疲労学会の定義によると、「過度の肉体的、精神的活動の後に起こる活動能力の減退状態」のことを疲労といいます。
そして、疲労状態の時に身体が発する不快感のことを、疲労感というそうです。
この不快感は、熱や痛みなどと同じように身体から発せられる危険信号と同じです。
つまり、疲労感を感じる=熱や痛みと同じように何らかの対処が必要ということになります!
この価値観を、今ここで覚えていきましょう!
なぜ疲労感を無視できるようになったのか?
犬猫は疲れたらすぐ休みます。小さい子供も疲れたらすぐに休みます。
なぜ大人になった私たちは疲れたら休む、ということができなくなっているのでしょうか。
それは、脳が発達したために、疲労感を隠すことができるようになってしまったからだそうです。
例えば、使命感や責任感、報酬の喜びややりがいなどが、疲労感を感じなくさせる大きな要因です。
また、電気や覚醒ドリンク剤の普及は物理的要因といえるでしょう。
しかし、その繰り返しで根本的な疲労は解決しているのか?と問いてみれば、誰もが首を横に振るでしょう。
その場しのぎでしかない対処は、いつか、さらに大きな代償となって返ってくる…そんな気がしませんか?
疲労感を防ぐ方法は?
1つ前の記事は対処法についてお伝えしました。
こちらでは、防ぐ方法についてお伝えしていきます!
1、適切な睡眠時間
どんなに短くても睡眠時間は必要です。6〜7時間の睡眠が良いと聞いたことがある人はいるかもしれませんが、万人に当てはまるものではありません。
あなたに合った睡眠時間を知ることが大切です。
例えば、あの有名な大谷選手は12時間寝るそうです。人によって体力の消耗量も違いますし、快・不快の感覚も異なります。
これを知るためには何度か実験をする必要がありますが、返って寝ることで疲労が溜まっているケースから脱却することもできますし、自分自身の生活ルーティンに自信を持つことができます。
2、適切な食事量や食べ物
どのくらいの量を食べると次の日に起きやすくなるのか、どの食べ物を食べると起きづらくなるのか、また、何時に食べると次の日が起きづらくならないか。
食事量・食事内容・食事時間で睡眠の質も変わります。
細かな栄養面に気をつけられる人はいいですが、もし難しい方は「適切な食事量」から変えていきましょう。その次に「食事時間」、その次に「食事内容」とトライしていきましょう。
人それぞれトライしやすいものがあるはずなので、順番は入れ替わっても問題ないです。
3、就寝前後のルーティン
寝る前にどんなルーティンがあるといいか、起きてからどんなルーティンがあるといいか、自分の行動を振り返りましょう。
例えば、私は朝のうちに掃除をすると気分が上がって1日過ごしやすくなりますし、仕事終わりも快適な気分になります。
あなたにとっての幸福ルーティンが見つかると、疲労感を溜めにくい生活になります。
まとめ
自分を知ることを諦めないで!
そのために、定期的にサロンにご来店いただくことをお勧めします。
最初のうちは2〜3週間1回のご来店をすることで、疲れやすいタイミングはいつなのか、どんなことがあると疲れやすいのかをしっかり把握します。
その後は3〜4週間に1回のご来店ペースにして、お客様の心身の変化を継続的に共有します。
身体と心とは切っても切り離せない付き合いものだからこそ、継続が大事です。
自分だけでは気付きにくいお疲れや心身の変化に、身体の声を聞くプロのセラピストをご活用ください!
ご来店予約はこちらから
関連エントリー
-
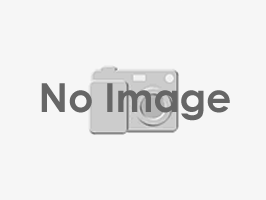 8/20〜8/26までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
8/20〜8/26までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
-
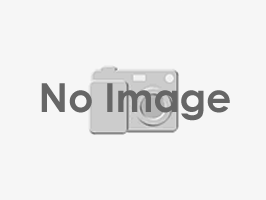 8/27〜9/2までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
8/27〜9/2までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
-
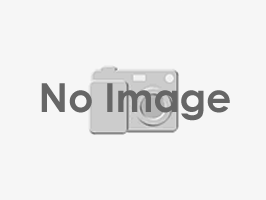 9/3〜9/9までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
9/3〜9/9までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
-
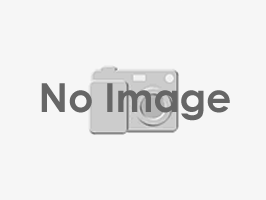 9/10〜9/16までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
9/10〜9/16までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
-
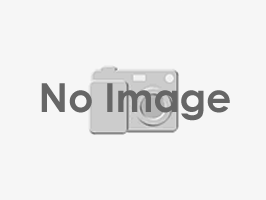 9/24〜9/30までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を
9/24〜9/30までのネット予約を開放しました
たくさんあるサロンの中から当サロンをお選びいただき、心より感謝いたします✨継続で通ってくださるお客様の予約枠を